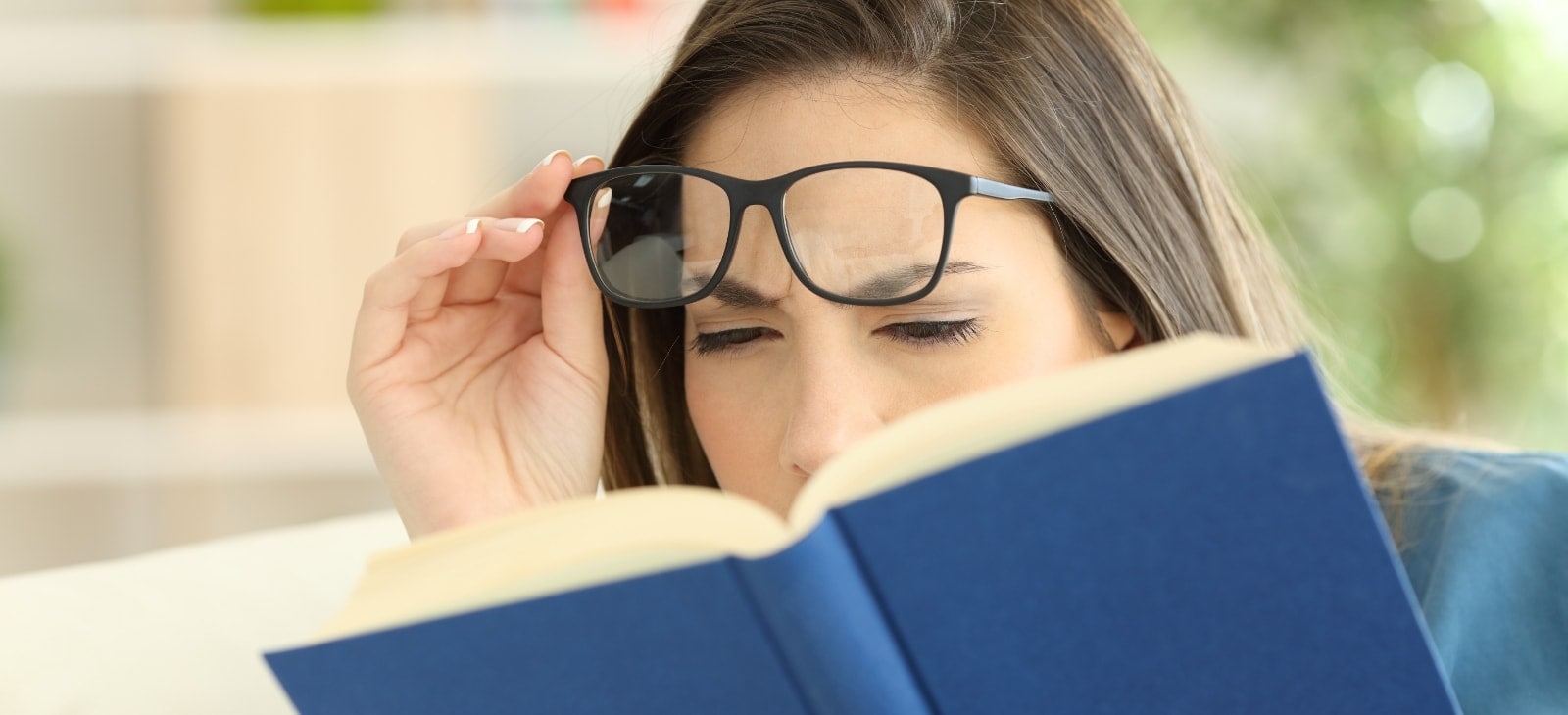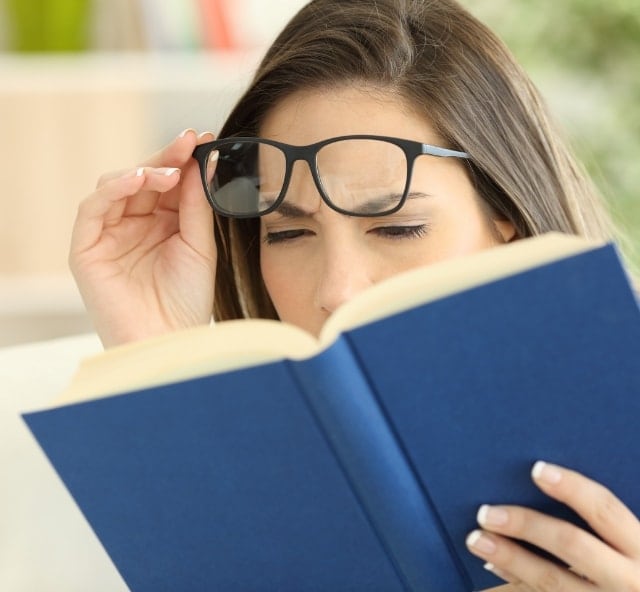自分のメガネやコンタクトの度数はわかるけれど、メガネのレンズの違いはあまりわからないという方も少なくありません。
ここでは、遠視・近視・乱視・老眼との違いや遠近両用メガネをかけるメリット等をご説明します。
遠視とは?近視・乱視・老眼との違いは?

瞳の奥にある水晶体は両凸レンズの形をしていて、瞳に入る光を和らげたり、目で見た映像に対してピントを合わせます。
その焦点を結ぶ位置によってどこにピントが合いやすいのかなどの違いで、遠視や近視・乱視・老眼など視界の見え方に変化があります。
遠視の見え方

「遠視」とは、本来焦点を合わせたい位置よりも奥でピントが合ってしまう状態です。
眼軸の長さや水晶体や角膜の屈折力など要因は様々です。
老眼と一緒で手前のものが見えにくい状態と思われがちですが、子供にも遠視は起こります。
矯正をしていない状態では、遠くも近くも見えづらく、目が疲れやすくなってしまいます。
軽度の場合は、遠くを見る分には少しのピント調整で済みますが、近くのものにピントを合わせるのが特に不得意な状態です。
近視が「ー」表記、遠視が「+」表記で度数表記されるようにレンズの形状も近視とは異なり、レンズをかけると虫眼鏡を覗いた時のように目が大きく見えるのが特徴です。
近視の見え方

遠くのものがぼやけて見える状態が「近視」で、「近眼」といった呼び方をする方もいます。
手前にピントが合いやすい状態なので近距離ははっきりと見えている方が多く、言い換えると遠くのものにピントを合わせるのが不得意な状態です。
そのため軽度の近視の方の中には、日常的にメガネを使用せず、車の運転や映画館に行く時だけメガネを使う方もいて、状況によって使い分けをすることが可能です。
自動車の運転免許では、一定の度数になるとメガネの着用が義務付けられています。
運転免許証に「眼鏡等」の条件がある場合、眼鏡やコンタクトレンズを装着して運転しなければなりません。
乱視の見え方

「乱視」とは、レンズの働きをする角膜や水晶体に歪みがあり、それによって焦点が合わない状態です。目の屈折力が方向によって異なるので、ピントがズレて、ぶれたりぼけたりして見えるのが特徴です。
瞳孔が広がりやすい暗い場所では、見え方のぼけが強く感じる傾向にあります。
眼鏡屋や眼科での視力検査の際に、時計のようなマークを見て縦や横どこかの方向が濃く見えていないか、均等に見えているかを問われるテストは、乱視のチェックの一部です。
老眼の見え方

「老眼」とはレンズの役割を持つ水晶体に対するピント調節機能が、年齢に応じて弱くなり、近くにピントが合わせにくくなる状態です。
水晶体は厚みを変えてピント調節をしますが、加齢によって水晶体の弾力性に変化が起こり、特に近くのものを見る際に厚くしようとする調節がうまくいかなくなっています。
そのため、読書や新聞・スマートフォンなど手元の小さな文字が見えづらくピントが合わせられなくなっていきます。
40代半ばごろから見え方に変化を感じる方が多く、遠距離は見え方に変化はなく、近距離がぼやけて見えるように感じます。
遠視を放っておくとどうなる?

遠くも近くもピントを合わせるのが得意ではなく、疲れやすい状態にある遠視は、放っておいてはいけません。
小さなお子さんでも遠視用のメガネをかけている姿を見かけるのは、視力測定で遠視だと分かったら放っておかずに、眼科を受診し度数にあったメガネを作っているからです。
それは、度数が強くなると斜視や弱視になる可能性があるためです。
度数が軽度であったとしても、終始ピントを合わせなくてはいけないので目に疲れを感じ、それに伴って頭痛やストレスを感じやすいというリスクもあります。
また子供の遠視は、物心ついた時からその見え方なので変化や異変を自覚しづらく、親への申告もなく見過ごされてしまう可能性もあります。
そうして気づかずに放置してしまうと、大人とは違った局面でのリスクが潜んでいます。
集中力が削がれてしまったり、それによってストレスやイライラを感じてしまったりすることもあり、勉強や学校生活でも支障が出ることもあります。
遠近両用メガネをかけるメリットは

遠近両用のメガネは、遠くも近くも両方見えやすくしてくれるメガネです。
遠くを見る用と近くを見る用のメガネを上下に2本かけているような状態で、用途に応じて掛け替える手間がなく一本で済むため便利です。
上部は遠くが見えやすいための度数、下部は近くが見えやすいための度数で作られていて、度数が累進しているので中間距離もスムーズなのが特徴です。
多くの場合はなだらかに度数が変化する「累進多焦点レンズ」で作られますが、中にはレンズの下部にわかりやすい切り替えの小窓部分がある「二重焦点(バイフォーカル)レンズ」もあります。
一本二役に悩みを解消してくれる遠近両用メガネは、天地の縦幅があるフレームで作ることがおすすめです。
「累進多焦点レンズ」は度数の変化が滑らかなので、見え方に慣れやすいのが特徴です。
遠近両用メガネがおすすめの人とは?老眼鏡との違いや選び方も解説
遠近両用メガネをかける際の注意点は?

遠近両用メガネを作る際には、黒目の位置を測って遠用の見え方の位置を決めて、そこから累進で度数変化をさせます。
そのため、かけ心地のフィッティングがとても重要です。
黒目の位置が度数の位置とズレると見えにくいので、定期的な調整も大切です。
また、最初のうちは見え方に慣れるまで足元の見え方や車の運転などが気になる方もいますので、徐々に慣らしていく必要があります。
視野の変化にスムーズに慣れるためにも、早いタイミングでの使用がおすすめです。
老眼は放っておくと眼精疲労や頭痛・肩こりなどのストレスにも影響しやすいので、「老眼鏡をかけるのはまだ抵抗がある」という方も、遠近両用でさりげなく手元の視野をサポートすると楽になります。
例えば、オフィスでの室内の見え方とパソコン作業、車の運転とカーナビなど、遠くと近くでピント調節に違和感を感じていたシーンでも、遠近両用メガネを使いこなせば快適になります。
遠近両用メガネのデメリットとは?購入前に知っておきたい注意点
JINSならあなたに合ったメガネを作れる!

JINSでは、遠近両用レンズも度数にかかわらず一定の追加料金で作ることができます。
遠近両用メガネは高いと感じていた方でも、シンプル価格で取り入れやすいのが魅力です。
遠近両用レンズの多くは、下部の周辺部分に歪みを感じることがあり、それらに慣れる必要があります。
JINSの遠近レンズなら、従来品よりも歪みが気になりにくいレンズ設計になっています。
遠用の視野が広いので近視の方の遠くの見え方もサポートしやすく、また中間部も見えやすいので室内での中間距離も快適です。
紫外線99%以上カット、撥水コート、反射防止コートで機能性や使い勝手の良さ、見え方の美しさも叶えてくれます。
まとめ

視力の見え方は環境や習慣、年齢などで変化します。
ただの疲れ目かなと思って放置すると、見え方やピント調節のストレスによって、意外なリスクが起こるかも知れません。
見え方に違和感を感じた時は、眼科もしくはメガネ販売店への相談がおすすめです。
遠視・近視・乱視・老眼や、パソコン・スマートフォンなどの生活習慣、眼精疲労の度合いなどを総合的に確認しながら、TPOやニーズにあった快適なメガネを選びましょう。
よくある質問
Q.遠視の場合、メガネは必要ですか?
適切なメガネでピントを合わせることで視力の快適な状態を維持できます。遠視のまま放置すると、目が疲れやすくなり、近くが見えにくくなります。
Q.遠近両用メガネは必要ですか?
遠近両用メガネは、遠くと近くの視力を一本で補正でき、日常生活が便利になります。特に中年以降の老眼症状や多焦点レンズへの不安を解消し、スムーズな視界切り替えが可能です。